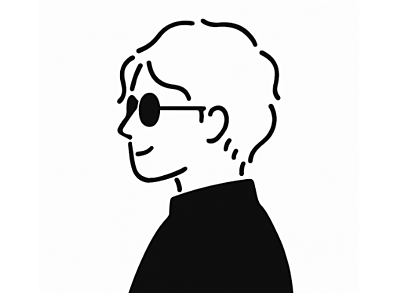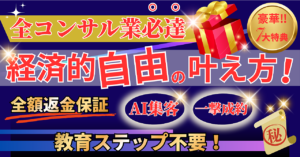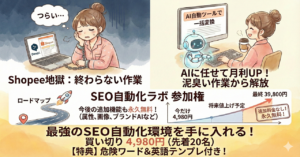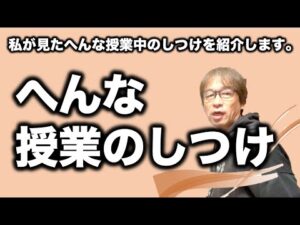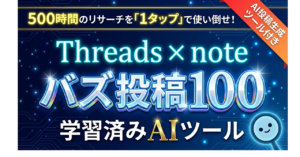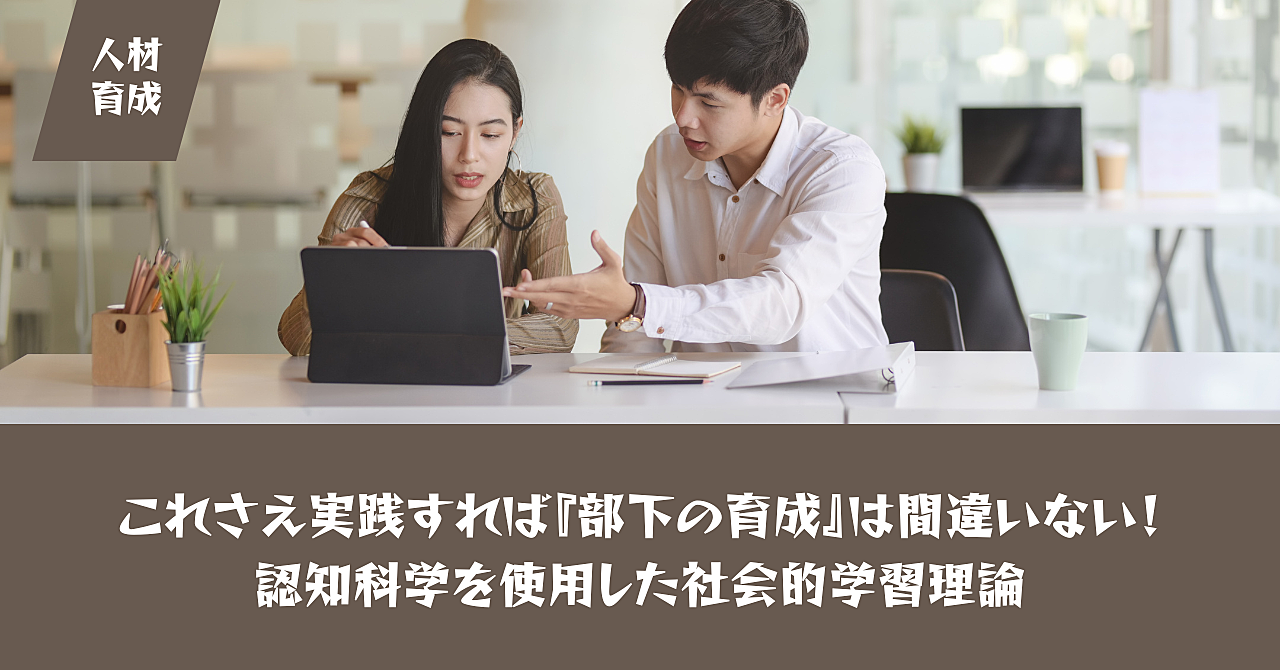
これさえ実践すれば『部下の育成』は間違いない!認知科学を使用した社会的学習理論
0 件のレビューがあります
平均スコア 0.0
✨ 「学び」は一人で頑張るもの?それとも…!「努力すれば必ず報われる」「人に頼らず、自分で乗り越えろ!」こんな言葉、誰しも一度は耳にしたことがあるはずです。もちろん、努力や根性は大切です。しかし、現実問題として、すべてを「一人の力」で成し遂げるのは、かなり非効率。むしろ、成長が遅
4,150 total views, 2 views today
この記事のレビュー
0 件のレビューがあります
平均スコア 0.0